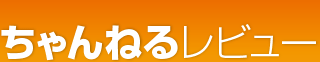2.67
2.67
| 5 | 693件 | ||
| 4 | 159件 | ||
| 3 | 156件 | ||
| 2 | 151件 | ||
| 1 | 1064件 | ||
| 合計 | 2223件 |
今週は家族で稼ごうという姿は良かったし、とんとん拍子にことが運ばないのもおもしろかったです。時間がかかっても本当の成功をこの姉妹が勝ちとったときは視聴者の私も嬉しいと思います。
花山さんが苦手と常子は言った。常子が苦手と私は思う。
おじさんは神の舌を持つ男になって旅立って行っちゃいました。
多分しばらく帰ってきません・・。
てつろうおじさんは他ドラマの撮影のために出たり入ったり、脚本家の都合のために出たり入ったりが忙しいですね(笑)
向井さん自身は少しお顔もシュッと引き締まってルックス的には前よりも良くなってる感じなのに、いまいち作品に恵まれませんね。気の毒です。といっても今はルックス・演技も良い20代・30代の若手俳優が飽和状態なので大変だとは思いますが、この朝ドラマの役を演じるに当たっては向井さんは普通にイケメンすぎだし勿体ない感じがします。
あの叔父さんは一年間もただ飯を喰って小橋家に居座っていたんですよね。次の雑誌のためお金は返さなくても良いなどとカッコよく言ってましたが、家賃と食費の代わりに紙代と印刷代くらい払っても、小橋家にバチは当たらない気がします。でも叔父さんの資金源は知りたいところではありますね。どんな人(それとも会社?)が貸してくれるのだろう?以前の借金は勝手に知り合いが名義を借りてたようだし、今のところ借金取りに追われている様子もないから今いち分からない。事業が失敗したあとに知り合いの農家を手伝っていたという鉄郎。農作物(貴重な卵も)を手土産に小橋家にやってきたくらいだから、嫌われたり追い出されたりではなかったんだろう。そして、ジーンズの情報を教えてくれたのは誰なのか?新しいビジネスを始める為にスグに舞鶴へ行かなきゃならない、と言ってたけど、声をかけてくれたのは誰なのか?どうも多方面かつ広範囲に知り合いがいるように思えるのですが、いったいどんな人脈を持っているのか?彼の周りには良い人も悪い人も集まってきてしまう。そんな感じがします。でも、その辺はきっと謎のままなんだろうなぁ。今度こそ一山当てるぞとサッサと舞鶴へ旅立って行きましたが、今度こそ成功できるのか?それともまた何処へさすらうのか?そして鉄郎のいる地域の本屋にも常子の本が並び、小橋家に電報が届く日はいつになるのだろうか?とりあえず、暫くはさようならのようです。また会う日までお元気で。
できの悪い月9よりクオリティが低い。特に人間描写と心理描写。
そこさえしっかりしていれば、まだ何とかかんとか見られようものを。
おじさんがいきなり出ていこうとしたとき、常子が
「えっええ・・なななな」みたいな驚き方してた・・・
どうもああいうところが気になるんですよ・・・
現代的すぎるというか。何と言っていいかわからないんだけど
非常な違和感を感じる!
今の時代ならいいんですけどね。気になっちゃうな~~~
視聴率落ちてる原因の一つかもね。
凄く面白いです。お金を稼いでかかを幸せにしたいと失敗を怖れず自分達で本を出す常子達。確かに無謀な面はあるかもしれないけれど、戦後のあの状況だからこそ確かに好機なのかも。素直に応援したいですね。
水田に教えられるまで常子は仙花紙の存在を知らなかったのは明らか。知っていれば、闇市で高値をふっかけられた時、おかしいと気づいたはず。当時、出版社はなんとか紙を調達していたと説明があったので、甲東出版では仙花紙を使っていなかったのでしょう。だから常子が知らない設定も不自然ではない。調べたところ、当時は出版会社に印刷用紙の配給があったのだとか。紙不足でなかなか行き届かなかったのは事実ですが。
「スタアの装ひ」初版の300部は一日で完売し大成功。常子のミスは再版にまた仙花紙を選んでしまったこと。おかげですぐボロボロになる本だと悪評がつき、競合商品の出現もあり、売れなくなってしまった。「私の管理不足」のくだりでは、その選択ミスを常子は自分の責任だと認めている。つまり、紙がこんなに早く劣化することに気づけなかったのが敗因だと。
既出だけど、こういう想定外の落とし穴は常子のように経験不足な新参者には付き物。この失敗エピソードは常子に盲点があったこと、つまり未熟さを描いている。だから経験豊富な助っ人が必要、ということで五反田が花山を紹介した。ストーリーとして辻褄は合っているし流れもいい。
出版の仕事は二度としないと言い切った花山だけど「スタアの装ひ」を買ったところをみると、常子の仕事ぶりが気になっているようだ。そんな花山を常子がどう口説き落として仲間に引き入れるのか?それと、水田がどんな形で常子たちを助けることになるのだろう?これからどんな話が待っているのか、楽しみ。
そうですね。五反田も花山は女性的な視点ももっていると言っていたので常子にアドバイスしてくれるといいのですがね。女性のための雑誌ときいて興味があるのかもしれませんね。花山。
五反田はわざと常子のことを花山にいったと思う。ペンをもつのをやめられると五反田も困るんじゃないのかな?業界に花山がいれば挿絵も描いてもらえるかもしれないし。
だから、そのセリフが矛盾の上に成り立つと言っている。
そんなにすぐ劣化しないし、管理もなにも購入する前、初見で紙質が悪いと解るレベルという話。
時代的に、モデルの方は仙花紙もその質の悪さもある程度知っていたのでは?
立派な御仏壇が映ると目の前で繰り広げられる光景を(とと)はどう思ってるんだろう・・・って真面目で実直だった(西島・とと )を思い出す。
と、同時にやりたいと思ったら後先考えずに櫓の上に上ってハラハラさせる幼い常子も思い出すのだ。
だから、常子なりに一念発起したら猪突猛進、突き進む姿は幼い頃と変わりない。見てる方には時として情がない、厚かましい、・・・理解し難いところも多々あるが鉄郎に乗せられたとしても出版すると決めたら脇目も振らずやり通す。常子らしい。
常子役の高畑さんが「常子は一歩も後ろに行かない人。ちょっとずつ分かってきたり、突然なるほどって分かったり長くやってないと分からない変化がある」とおっしゃってられるが誠に正直な気持ちだと思う。
まあ、演者もこれじゃあ目をパチパチするしかなかっただろう。
次週からは本当に花山と二人三脚で出版業を起業していく佳境に入っていく。NHKに恩返し・・・って出演される唐沢さんの花山がどう演出されてゆくのか・・・妙な妄想などはもういらない。役者さん達の演技力だけで見てる側を引き込ませて欲しい。
仙花紙で作ったカストリ雑誌が現存しているのは知っていますが、保存状態は良くないようですよ。仙花紙は劣化しやすいですから。お客さんの立場で考えると、字が消えてたり破れやすい本は嫌だと思うのは当然。
紙質が悪いのは分かっていても、それほど劣化が激しいとまでは予想できなかったってことでしょ。そこまで見抜けなかった常子の目が節穴だったってこと。本人も非を認めているし、べつに変じゃない。
七十年前の質の悪い紙の保存状態が悪いのなんて当たり前でしょうに。
実際はそんな極端な劣化をしないという事です。
モデルの方は本当に知らなかったのか?知っていたなら何故常子はこんな無知な設定にされたのか?反省させたり苦労させたかったから?
実際スタイルブック創刊号は花森と共に作っていてすぐ真似されて暮らしの手帳に切り替わっているので、順序を変える事により矛盾が多くのなっている。
カストリ以外の雑誌も多くは仙花紙ですよ。
小説も仙花紙。
常子が、管理が甘かったと言ってたのがイマイチ意味がわかりません
野ざらしにでもして出荷前にボロボロにしてしまったんだろうか。
以前から本の扱いが荒っぽい常子ならやりそうな気も。。
開業する蓄えが有るのに、物書きを目指す鞠子が仙花紙の新刊小説一冊さえ所持していない読んでいない目にしていないという不思議。
管理が甘いの管理は、紙の保存の仕方が悪かったって意味じゃなく、すぐボロボロになるような紙を選んだ自分のビジネスマネジメントが甘かったって意味じゃ?
紙質の違いは買う時にスグに分かったと思いますよ。でも安いからこんなもんだろうと妥協したんじゃないかしら。印刷用紙を手に入れるのは相当難しいようだったし、質は悪くても紙があるだけマシ、そういえば闇市で売ってる雑誌はこの紙だよ、って感じでしょうか。見た目や感触の違いは分かっても、耐久性は使ってみないと分らなかったという話ですよね。実際はそこまで劣化は酷くないというご指摘もあるようですが、ドラマでは粗悪な紙であることを強調したということですかね。それにしても、本来は見た目の違いは、買う時に気づくのではなく、見てスグ気づく方が自然ですよね。水田の出番をつくるために、紙の束の近くにいる常子ではなく彼が気づく、という展開にしたのでしょう。わたし的には今週一番の突っ込みどころでしたが、いかにもドラマらしい次の続きを想像させる突っ込みどころだったので許す・・・って感じでしょうか。それにしても水田さん、露天商組合の経理の人でしったっけ?遠目ですぐに指摘(仙花紙であること、相場、入手ルート)ができるという事は、どんな経歴があり今は具体的にどんな仕事をしているだろう?しつこくナレで言っていた小橋家との関わりや鞠子との事よりも、今はそっちの方が興味がある。
仙花紙は確かに質の悪い紙だけど
何もしてないのに一ヶ月でボロボロになるほど酷い物でも無いはずなんだけどなぁ。
仙花紙といえば全国一律どれも全く同じレベルの低品質なのでしょうか?
実際ドラマ内の表現ではポロポロ剥がれていて、あれではもう売れないですよね。
いくら仙花紙で作られた本が出回ってた証拠をここにあげたって、ドラマ内では売り物にならないって話になってるんだから。
仙花紙の中でもピンきりあって常子が買ったものは印刷したらああなってしまったって事でいいんじゃないの。
だからね、実際はそんなにすぐボロボロにならないの。
少なくとも小説印刷して読み終えるまではもつ紙なの。
状態悪くても七十年後にも本の形を保っているの。
どうしてそんな短時間でボロボロ設定にした?
そして実際は花森と最初から一緒に作ったから、大橋さんが仙花紙の耐久性も知らなかったなんて事もないの。
何でわざわざ知らなかった事にしちゃったの?
何でも史実通りとは言わないけど、ここいじる所?
常子が「管理が甘かった」と言ってるんだから
保存方法を間違えたってことでいいんじゃないの?
他に管理のしようがないと思うんだが
金がなく手っ取り早く闇で仕入れた安い紙を使ったらぼろぼろになったというのが終戦直後の話らしくていいではありませんか。小橋家だけでは出版は無理でしょう。花山さんの編集の力とちらっと出てきた電車男さんが値段に詳しかったから力を貸してくれるんでしょう。失敗しながらも脇を固めて暮らしの手帖へと進みそうで楽しみです。
ボロボロになった時には本が出来上がって一か月経ってたよ。仙花紙がどれほど長持ちするのかは実際知らないけど、このドラマでは劣悪な紙質だったことが強調されているんだなと思ってる。
貧乏設定の上に鞠子を失業させちゃってるんで
史実通りには出来ないというのもあるんだろうけど
花山の存在価値を高めるために史実に無い失敗をさせてるんでしょうね。
なにも紙をボロボロにしなくても、最初の300部から売れませんでした、の方がそこから史実に近付けられたのに。
だからね、と書かれた人に言いたいんですが、仙花紙の中にも不良品ってないんですか?
戦後のあの時代、仙花紙の中でも特に質の悪いものも存在したんじゃないかって書いたんですが。
あなたは戦後の時代に生産されたすべての仙花紙の品質をチェックしたわけじゃないでしょう。
仮にもモチーフとなった雑誌があるのに、そこまで劣悪を強調する必要性は?
実際のスタイルブック創刊号がヶ月でボロボロになるような割高雑誌だったなら話は別だが、そうでないなら失礼では済まない。
そこまで質の悪い紙なら印刷する前からボロボロになってたでしょ。
紙買ってから印刷まで結構時間あった気がするぞ。
スタイルブック創刊号、非常に状態の良いものが綺麗に残っていますよ。
仙花紙の中でも劣悪な仙花紙ではないようです。
なんでボロボロ強調したのでしょうね。
売れなかった理由を紙のせいにするためかな。
内容は悪く無いとか花山に言わせるんでしょう。
実際のスタイルブック創刊号はスケールの大きな話なのに
スタアの装ひはずいぶん小さい話になっちゃったね。しかもボロボロにされるとは…
やっぱり早めにモチーフの看板も下ろしておくべきだったのではないかと。
これはあくまでもフィクション。史実はモチーフ、元ネタ。同一視しちゃだめ、っていうのは折り込み済みですよ。このドラマでは常子の本の劣化が早かったって話。大橋鎭子さんのスタイルブックがそうだったと言ってるわけじゃない。
スタアの装いがボロボロになる話にしたのは、常子をピンチに立たせるためと強力な助っ人をリクルートするためでは?この話はその方向でおもしろくなってきたと思います。
初版300部は完売。気をよくして強気の千部増刷。が、すぐに同じような雑誌が安価で出回ったため売れ残ってしまう。更に紙の劣化が激しく在庫が売れる希望はもはやない。でも全くのダメダメではなく、初版が売れて同業者がすぐ真似をしたのは大きいと思います。未熟でも人を惹きつける何かがあったということでしょう。何の魅力も将来性も感じられなかったら、常子の理想だけであの花山を口説くことはできないと思います。突っ込みどころ満載のTK出版ですが、ここからどうテコ入れをするのか?来週が楽しみです。
まとめると、日本の製紙業者を舐めるなって事だ。
常子をピンチに立たせる為の現実には考えにくいボロボロ設定、この意図が透けすぎて白ける人がいてもしょうがない。
期待して見た暮らしの手帖愛読者が首を傾げてもしょうがない。
売れたのは女性の興味を引く内容だったからであり、売れなくなったのは紙のせいではなく、誰にでもスグに真似されてしまうような内容だったからでしょう。紙が劣化したせいで、700部以上ある在庫が売り切るのは絶望的になったということです。常子のビジネスの師匠である鉄郎は、売れそうなものに対するアンテナは鋭いが、売れた後の次の一手が打てない人であり、ピンチになるとすぐやめてしまう。そこを乗り越えることをしないから何をやっても上手くいかないのでは?と私は想像しています。ジーンズもスグに諦めていた。熱意があればそこで諦めることはしないと思うのです。おそらく今、常子が乗り越える壁はそこなのでしょう。とは言っても、あの三姉妹でとりあえずそこまでは出来たっていうのは、大きな失敗ではありますが大きな収穫でもあったのではと思います。
実際のスタイルブックは売れたのでは無く、売ったのだ。
スタアの装ひは売れた。そしてボロボロになった。
さて、ここからどうする脚本家。
闇市でたくましく働く女性を見、叔父さんの言葉に触発されて、リスクを覚悟で賭けに出た常子はやはりすごいと思います。そこで女性の役に立つ雑誌で思いついたのが、洋服のスタイル本。着眼点もいいし、だから最初飛ぶように売れたのだと思います。ただ叔父さんが調達してくれるとはいえ、資金は十分ではない。だから常子は安い仙花紙に手を出したのでしょう。ただ、あれほど材質がひどくボロボロになるとは予想できなかった。だから失敗した。それだけのことでしょう。まったく違和感のない流れだと思います。
少なくとも、ドラマの中での整合性は取れています。
値段の高さと紙質の悪さ。そこが第一の問題点のようですが、次回作でそれを改善したとしても、今のままではライバル雑誌に勝てる保証がありません。だから甲東出版の諸先輩に相談したのも自然です。ただ文芸専門誌なので女性向け雑誌のことはわからない。そこで五反田が花山を紹介してくれたのですよね。
結局、編集者の経験があるとはいえ、常子はまだ自分だけで独立してやるには未熟だったということ。それが分かった経験だと思います。
そんな常子に編集のプロである花山がどんなアドバイスをしてくれるのかとても楽しみですが、その前に花山の出版という仕事に関する葛藤が描かれそうですね。
「邪魔するな。帰れ。3度も言わせるな!!」といきなり怒鳴りつけらた花山に常子が苦手意識を持つのも不思議はないと思います。でも今は藁にもすがりつきたい時。ペンを折るという花山の固い決意を常子がどう崩し協力を得られるのか、注目したいです。
色々細かい批判が多いようですが、私は自然に楽しめています。
これからも小橋3姉妹の奮闘ぶりを応援します。
壇ナレーターへお願い
たまに青柳家、森田家の近況も伝えてくれ。
めっちゃつまらないよ。
これからは面白くなるかな。
私は苦手。最近はやばいね。色々と…。
本当につまらない。もはや打ち切りレベル。
常子みたいな若い娘が、独立していきなりとんとん拍子に成功じゃあ非現実的すぎて白々しい。納得のつまずきじゃないかな。
このドラマはちゃんと挫折や苦労も描いてくれるのがいいですね。
その中でどう成功への道を切り拓くか。それが見どころだと思います。
来週はそのカギとなる花山が本格的登場でとても楽しみ。
戦時中、戦意高揚の標語を作って国民を煽った心の葛藤もあるでしょう。
終戦の日の花山の沈痛な表情が忘れられません。
もう出版には関わらないという決意は相当のものに見えました。
それでも常子の作った雑誌は闇市で買って目を通していた。
そんな花山の心情が来週どう描かれるか期待します。
無理に失敗させる必要は無いのにね。
誰が作ろうが売れるものは売れる。
それを無理やり失敗物語にしようとするから
出版社勤務の実務経験が無かったかのように
紙の仕入先も知らず、相場も知らず、管理も出来ず?のおかしな話になる。
その上、こっちは増刷するだけの間に
バクリ雑誌が大量に刷り上がっているという奇跡まで。
これからも数倍早く本を作るパクリ軍団と戦っていくの?
感動したことがない。共感して泣いた事がない。
先週は、常子が甲東出版を退職し、「スタアの装ひ」というファッション雑誌を創刊しましたが、それを観ていて、私は「まれ」で主人公の希が横浜でのパティシエ修業から能登へ戻り、数か月の休業を経て能登でケーキ屋を開くまでの一連の場面を思い出しました。
ところで、希のこの間の行動や描与については、放送当時様々な意見が出ていましたが、少なくとも希のパティシエとしての力量については、パティシエの世界大会で優勝経験のある池畑大悟の経営するマシェリシュシュで4年半修業し、最後の1年はスーシェフを務めるなど、世界最高レベルであろう大悟からも全幅の信頼を置かれるようになって、ケーキ作りの高いスキルは勿論、経理その他の事務の知識も身に付けていたことが視聴者にも分かるようになっていました。一方、常子については、5年程甲東出版に勤めていたこと、うち最後の2年は貸本業務をしていたことなどは分かるものの、どの程度のスキルや知識を身につけたのかが明確になっていませんし、視聴者にも見当が付きません。
次いで、独立から開業までの過程にしても、希の場合は、マシェリシュシュを退職し夫の圭太をサポートするために能登へ戻った理由も、失踪した父の徹が残していった計画書を元にケーキ屋を開く決意した理由も、過疎化の進んだ能登の現実を曲がりなりにも取り上げ、希や圭太、徹らをしっかり造型して描写してきたりしたことで、賛否はともかく、少なくとも希なら有り得ない行動ではないと視聴者に思わせるだけの描写はできていました。一方、常子については、服飾は勿論、生活の知恵や出版物を自ら出すことに高い関心を持っているように十分描写されてなかったところへ、唐突に「甲東出版では自分の作りたい雑誌が作れません。売上も自分のものになりません。」と退職を申し出たことで、世話になった人に対し後ろ足で砂を掛けるような非礼で金に汚い人物であるかのような印象を一部の視聴者から持たれることになってしまいました。
さらに開業までにしても、希の場合は、開業資金の見積りから融資を受けるまでの過程が、農協での相談窓口になったみのりへの融資相談や圭太を保証人にした消費貸借契約書への署名捺印の場面だけでなく、具体的な金額を明示したり、見積りでは一部の備品を資金の関係で家庭用のものにすることまで含めて描かれていました。また、店名を決める過程についても、当初はフランス語で小さな魔女を意味する「プティット・ソルシエール」と予定していたのを、「フランス語の文法に忠実に従って『プティット』にしたのでは消費者が分かりにくい。『プチ』の方がよい。」という一子の意見で「プチ・ソルシエール」とし、フランス語表記は当初の予定通り「petite sorciere」(最後から2番目のeの上に右下へ真っすぐ向いた記号が付く)と決めるところまで描かれていました。なお、この店名は、希がパティシエになりたいと思うようになった原点である5歳の誕生日に買ってもらったケーキの上に載っていた魔女姫人形に由来します。この命名の場面は、経営者が直面する、理想の追求と利益を出すことの必要性との間での折り合いの付け方を分かりやすく描き、また、希にとっての魔女姫人形の重要性を端的に示していて、非常に良かったと思っています。一方、常子については、収支見通しを立てる場面も出てきませんでしたし、雑誌や会社の名前も、鞠子が「装ひ」と言ったのを受けて、鉄郎が「人々に夢を与えなければいけないから『スタアの装ひ』だ。」というようなことを言ったことで、雑誌名ばかりか、その勢いで「KT出版」という会社名まで決まってしまいました。この一連の描写からは、常子の内面も人生もさっぱり見えてきません。
このように、希のケーキ屋開業については、独立・開業するまでにスキルや知識を身につけるまでの過程、開業までの苦労などが、個々の場面の描写の是非はともかく、少なくとも基本的な部分についてはしっかり描かれていましたし、動機もはっきりしていました。このことは、政春(マッサン)、純(純と愛)、梅子(梅ちゃん先生)、波美(ウェルかめ)、瞳(瞳)といった他の朝ドラの主人公の独立・開業についても、程度や描き方に差はあっても、同様のことが言えると思います。
このように、今回の常子の出版社設立ほど独立・起業できるだけのスキルや知識、動機の分かりにくい朝ドラの主人公の独立・起業は、少なくとも私には他に思い浮かびません。「まれ」を否定的に評価し、「とと姉ちゃん」を肯定的に評価し楽しく観ておられる方には、申し訳ありませんが、私はそのようなことを思った次第です。
☆をつけるために、何か感想を書かないといけないんだけど、特に印象に残ったところがないというのが感想です。
苦労もしないで出来る雑誌は、誰だって作れるというだけ。それを、1000部を作るといって、にやつく常子の顔がヒロインとは思えないほど不快。常子は、ととに似ているのではなく、おじと同じ感性なんだと思う。もう向井さんは出演しないので、明日かおじねぇちゃんとタイトルを変えれば、視聴者は納得して見ることが出来ると
思います‼
出版社にいたなら紙は問屋で格安で仕入れる事など一般的で常識だし、問屋に掛け合ったなら紙の種類や性質についても教えて貰えるはず。
仙花紙本についても会社でそういう話題になって然るべきなのに、全く無し。
常子が出版社にいた数年間に積み重ねていたはずのスキルや知識が皆無になっていて、次に全く生かされず繋がっていない。
あり得ない失敗を唐突にさせるより、日々のささやかな経験やスキルアップ、出版社のやりとりが雑誌作りに発揮される作りにすれば良かったのに花山を印象付ける為に(本来はなかった)失敗ありきで事を進めたから常子を無知にするしかなかったのか。
残念です。
現代ではなく戦争直後の時代の話だよ。闇市で物を売っている人たちのように飛び込むように行動しなければ、あの時代は何もできないで飢え死にでしょう。常子が配給をまっていても仕方ないという言葉にも常子の行動が表されていると思うな。最初から失敗しないで行動をおこそうとする人って事業主にはなれないだろうし、失敗するとわかれば行動しないというのは現代人に多いですね。闇市のパクリもそうだけど、常子の生きている時代は生き残りを賭けて日々をくらしていると思うので現代人と比べられてもね。
実際の戦争直後のモデルさんがしていない行動・失敗なのに、戦争直後らしい行動と言われても、それこそ現代人的イメージなのではと思ってしまいます。すみません。
戦後一年といっても、紙問屋は回っていたし、出版社との横繋がりもあるので、戦後すぐ=即闇市はおかしいんですよ。
断られるにしても一度は問屋に問い合わせ紙の知識を得るのが普通。(仙花紙は問屋にあるのだから。)
多分花山と組んでから紙のツテを作りたかったので、常子を無能設定にしたのでしょうね。
スポンサーリンク