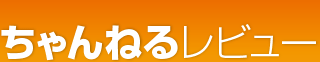4.05
4.05
| 5 | 432件 | ||
| 4 | 161件 | ||
| 3 | 50件 | ||
| 2 | 21件 | ||
| 1 | 101件 | ||
| 合計 | 765件 |
『直虎』での井伊直親(三浦春馬)・直政(菅田将暉)は素晴らしかった(脚本は半分ダメだったけど)が、今回の井伊直弼は、文化・教養人の香りがしないねぇ。なんでこの人? という感じ。
>国の未来を憂いて動いたのは、老い先の短い、地位の高い高齢者ではなく、
フランスの七月革命に参加した老ラファイエット、パリコミューンでマルクスから気高い老人と言われたブランキとかもいます。老い先の短いと言うのはちょっと表現に難があると思います。
このドラマめちゃ面白い。
慶喜の顔を初めて見たとき、面白過ぎてコーヒー吹き出してしまいました。
栄一の漢詩の朗読。上手過ぎて笑い転げました。
キュルキュルとかキュン キュン キュンキュン いってるBGMが、自動車のバッテリーか弱っててエンジンがかかりにくい時の音に似てると気付いた。
なぜ似てるのだろう。バッテリー上がりが近いのは…。
ここでの安政の大獄は家定の遺言てことになるのか。
幸せの絶頂の栄一と奈落の底に突き落とされた慶喜との
高低差が凄かった。
役者陣の演技がおせじでも上手くなく、それがあるため
せっかくの感動的なはずの内容もしっくりいってない様子。
やはり主演が渋沢とは遠くかけ離れたルックスの持ち主。
渋沢栄一の若いころの写真見ると結構イケメン。
男の人の顔も変わるからね。
でも年行ってからの顔もお札になるだけあっていい顔だと思う。
記者に囲まれてえらそーに語る人の顔じゃない。
内からも外からもワーワー言ってきて井伊直弼も
大変だったでしょうね。
安政の大獄の前後の話は歴史番組等で見たくなりました
>キュルキュルキュンキュンキュン
そんな音、してましたか?
あまり気がつかず、というかBGMまで神経が行かない鈍感なのか、今日は休みでもう一度録画を見てみます。
しかし皆さん色々とよく気がつき参考になります。
理知に富んだ渋澤栄一、なかなか見応えのある大河、日曜夜の楽しみになりました。
歴史ものは突拍子もない解釈の本がまことしやかに書かれて売られていたりするようだから、気を付けようと思う。
多くの人が見て検証されているようなドラマで歴史を知ることはいいと思う。
草彅剛は武士の髷頭姿だとカッコいいね。
普段の草彅剛は、正面にアデランスしているのがとても不自然な感じなので、もっと自然にカツラ、または増毛できないのかな〜って思っていたので。
時代劇のオファーが今後増えるかも。
草彅剛はいいね!唯一無二だ。
有吉弘行が草彅を『えら呼吸』と評したが、異端は魅せる。これからも期待する。
橋本愛が下手。
土曜の再放送を観ました。ますます面白味を感じます。
とっかかりが肩肘張らず物語に入りやすい。
引き付けられるのは見所も楽しみに、キャストも合う。
平九郎 もっと出番増やして
渋沢栄一がどのぐらい偉いか?まだよく分からない。
どちらのパートも面白くて、あっという間に終わってしまいます。
アメリカやヨーロッパよりず~っと文明の遅れていた日本は、開国もやむなし。
アメリカとか軍艦で来てるのに、日本では刀振り回して対抗してどうする!
>アメリカやヨーロッパよりず~っと文明の遅れていた日本
産業革命が起き物質機械文明が進んでたアメリカやヨーロッパより、と言う意味ですね。この頃はまだ南部アメリカでは黒人奴隷の売買があり、帝政ロシアでは農奴がいました。また、日本の高い精神文化に憧れ明治に帰化した小泉八雲のような人もいますから。
奴隷制度と文明の発達は、関係ない。
むしろ、奴隷制度があったからこそ、効率的に文明が発達したと言える。
もちろん、差別がいけない。ということは常識だが。
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)1人ぐらいでは、「日本がヨーロッパと比べて高い精神文化だった」証明にはならないと思う。
>奴隷制度と文明の発達は、関係ない。
精神的文明が遅れていたと言うことになるでしょう。
農民が自由主義的商品経済に組み込まれた西欧がユンケル地主制度のプロイセンや農奴制度のロシアに優れてたと言うことですから。
>ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)1人ぐらいでは、
後にはドナルド・キーン、クロード・チアリとかが帰化しています。ワビサビに代表される日本文化への憧れを言ってますね。
日本にも小作制度があり、また、武士や裕福な農民には家人みたいな奴隷に近い人々がいました。
3人なんていうのも数に入らないと思います。
日本は精神文化では古来から儒教の教えや老荘の思想など、中国文化を取り入れ、江戸時代にも盛んでした。
>日本にも小作制度があり、また、武士や裕福な農民には家人みたいな奴隷に近い人々がいました。
ですから、日本が産業構造が優れていたとは書いてません。欧米でも遅れた地域があたと言うことをユンケル地主制度やロシアの農奴制について書きました。小作人は黒人奴隷のような市場で売買される存在ではないですよ。中間のような武家奉公人も然りです。
>3人なんていうのも数に入らないと思います。
著名な人物を列挙しただけで、例示列挙をすべてを網羅したと考えるのは揚げ足取りでは?
もっと多くの欧米人が日本文化を礼賛していますね。ワビサビは日本独自の文化で中国とは切り離した方がいいかと思います。
なんにでも例外があり3人なんて、誤差のうちだと思います。
明治になってから、夏目漱石をはじめたくさんの人が西欧文学の影響を受けました。
固定観念にとらわれずに、勉強してほしいと思います。
>固定観念にとらわれずに、勉強してほしいと思います。
それはあなたのことですよ。非常に上から目線ですがこちらの問いかけははぐらかしてまともに答えようとしてませんね。
三人のみだなんて誰も言っていませんし。
司馬遼太郎ばかり読んでいたので、
今回謎だった水戸藩が描かれていて面白い。
また、栄一が裕福な農家なので、考え方が
武士にない後年の活動に繋がるのも見もの。
ただ、慶喜役の方はミスキャストだと思う。
シンセのBGM、うるさいわぁ( ̄△ ̄)。
ちょっと勢いがなくなってきたかな。
今後の展開に期待。
井伊直弼、討たれる。
『直虎』の井伊直親(三浦春馬)の「井伊は……どっちだ」思い出した。
「花の生涯」を除けば、大河の中では丁寧に桜田門外の変を描写していた。一方で、安政の大獄は殆ど描写なし。井伊直弼がいい人だった「篤姫」と似た扱い。
斉昭の死は「徳川慶喜」が眠るような最期だったのに対して憤死と言っていい。
出演陣が過去の大河に比べ豪華なので重厚感はある。
血洗島村の若者はいきり野郎しかいないのか。漢詩を読むくらいだから、もう少し教養があってもいいと思うが。
草彅剛さんが演じる徳川慶喜が秀逸でした。謹慎で閉じこもり自分自身を戒めて葛藤したり平岡円四郎を気遣ったり前回は美賀君に弱音をみせたり父徳川斉昭が亡くなり悲しさに嗚咽するなど迫真の演技が人間慶喜を見事に表現しました。これから志に目覚め立派な将軍として活躍する慶喜を草彅さんの演技と共に楽しみになって来ました。
井伊大老の懐刀の長野主善をほんの少しでいいから出して欲しかったな。そして平岡円四郎との対話シーンみたいのを描かいてもらいたかった。そうすれば円四郎の見せ場が出来たのに。キャストは玉山鉄二さんが適役だと個人的に思いますけど。
江戸城無血開城までは面白く見られそう。
その後が、吉沢亮さんの正念場だ!
吉沢亮君の熱演、いいですね。
凄いことやる人のパワーがみなぎっている。
家茂役・磯村勇人君が上品で落ち着きがあり、惹かれます。
円四郎役にマッサン、私もいいと思いました。
堤真一さんは好きな俳優ですが、殿に仕える家臣にはちょっと見えない気がして・・・
木村佳乃奥さんと話す際は江戸っ子べらんめえでも構わないが、お屋敷ではあんな話し方しないんじゃないかなといつも思います。殿に対してありゃあしませんぜぇなんて違和感があります。
斉昭のラブシーン必要だった?
奥方を尊敬し、すごーく愛してたのはわかりますよ、でも、演じる俳優にもよるんだけどなあ。栄一だったら、OKだけどね。あんまり気をてらった事をやらなくてもいいんだけど。
反対にべらんめぇの江戸弁は、確かに違和感あるけど、今までの歌舞伎口調の台詞を自然な形にもっていってるのかも。時代劇ドラマで侍はこうだ!ってイメージ植え付けられてるから、どれがホントかわからない。最近の大河は新しい史実をもとに描くことが多くなりましたよね。
麒麟が来るも、衣装がハデだったけど、実はこの時代、カラフルな着物を楽しんでたんじゃないか?ということで、武士もカラフルな着物姿で目も楽しませてもらいました。
もう、幕末だし、日本語は時代でコロコロ変わっていくしね。このドラマはこういう解釈なんだなと思ってみてるけど、斉昭のラブシーンは、やり過ぎ!
昭和の男だって、愛妻と別れる時、キスしないよ!
そーいうインパクト、このドラマ要らないから!
いつ見ても、円四郎の堤真一さんがしっくり来ない。あの役に合ってなくて浮いているような気がする。
慶喜の小姓になったのは、望まない役職だったというから、違和感が有って良いのかな?とも思うけど。
貧乏でも旗本の武士なんだから、住んでいる所からしてあんなに町人ぽかったとは考えてにくい。
それに木村佳乃さんも、服装、言葉使い、振る舞いが全然武家の妻らしく見えない。
キスシーン必要?
朝ドラかい
木村佳乃も堤真一もキ○ンビールのCM出てるから、麒麟がくるじゃないけど、(新)一万円札使ってビール買ってってことじゃないの(+_+)。
>老い先の短いと言うのはちょっと表現に難があると思います。
このドラマの背景である、幕末期の倒幕に関する話をしているのであって、世界中の革命一般の話でないくらいは解りそうなものですが。
平家打倒に真っ先に立ち上がった源氏の源三位頼政は、76歳の高齢で決起して、平等院の有る宇治川の合戦に敗れ自害しています。鎌倉幕府打倒の時も足利一門は老人も含めて皆戦っています。侍は藩や源氏と言った大きなくくりで目的が一致している場合は、総力を挙げて戦うものなのです。戊辰戦争で最期まで戦って敗れた会津藩も、「このご時世に京都守護職を受けるのは、薪を背負って火に飛び込むようなもの」と、家老に猛反対されたのに藩主松平容保が暴走し、家来達は泣く泣く従ってあの悲劇が起きました。
幕末の場合は倒幕できなければ「藩の改易=失業或いは死」なので、藩の中でも討幕派と佐幕派に別れ、高齢な藩士は敢えて危険を冒す事に反対するのは当然なのです。だから未来がある若者達が率先して討幕派になり、佐幕派との権力争いに勝って藩の主導権を握って倒幕に一本化したのです。その際若くして亡くなった人達の年齢は分かっているので、幕末は実年齢と極端に違う役者は使うべきではないのです。まして45歳で殺された井伊直弼の場合、描かれたのが出てきて死ぬまでのわずか2年間だけなので、50代の役者では誤解を与えてしまいます。
先週、井伊直弼が大老になったと思ったら、今週はもう2年後の桜田門外の変で面食らった。しかもその理由が、「幕府に逆らった攘夷派の水戸のTOPは謹慎ね。他の連中は死罪のお仕置きよ」、と「戊午の密勅」の説明が無いから謹慎と言う、単純な理由で起きたと誤解されかねない。戊午の密勅とは孝明天皇が、勝手に幕政改革を直接各藩に下したもので、それを幕府が怒って水戸藩にも返せと命じ、「期限までに返さないと例え御三家様でも改易よ」と言われた藩士達が怒り狂ったのが原因だ。幕末の一大事件をこうもあっさり単純化されると、この先もこの脚本家は経済の話よりも栄一の三人の妾と本妻の確執でも丁寧に面白おかしく描きそうな気がしてきた。
幕府側の尊王攘夷への弾圧と反発、そして桜田門外の変で、
水戸藩の状況が解りやすくて描かれていて興味深かったです。
使者達が暗殺されて怒った外国との武力衝突も扱われるのか、
次回も楽しみです。
最新式の武力に自分たちが完敗していくのを見て、今のままでは攘夷は難しいと考えるようになり、
「天皇の言うとおり、幕府も諸藩も一致団結して、外国の技術を取り入れつつ外国に対抗しないといけない」と考えるようになります。
龍馬伝では、松平春嶽、山内容堂、吉田東洋役の俳優さんが、みんな60代半ばから70代始めの人が演じていた。
でも実際の彼らの年齢は大政奉還の時でさえ40代。
(吉田東洋は大政奉還より前に46歳位で暗殺されている)
山内容堂役の近藤正臣さんは最初から白髪だったような?
龍馬伝放送当時、知らなかったので、みんなあんな爺さんだったんだ、と勘違いして見ていた。
まあ主役の龍馬の福山さんが40代だったからそのバランスからかなあ。
平岡円四郎の妻、やす(木村佳乃)は、武家じゃないみたいですよ。吉原の売れっ子芸者って設定ですね。だから、やす は気品がなくてもしょうがないかもです。
この先水戸藩の行く末が心配じゃ、
と言う斉昭の台詞がよかった。
桜田門外の変、斉昭の死によって、水戸藩は事実上の壊滅状態になっていく。
だいたいからして、尊王思想というものは、天皇を中心とした中央集権国家を創るべきという思想。拠って徳川幕藩体制というものとは対立概念であるにもかかわらず、その尊王思想が徳川御三家から発生したということがそもそも矛盾している。
したがって、この後水戸藩が事実上の壊滅状態に向かっていくことは、理論的には必然と言える。
スポンサーリンク