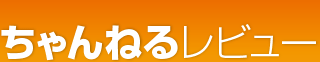3.38
3.38
| 5 | 1428件 | ||
| 4 | 124件 | ||
| 3 | 62件 | ||
| 2 | 111件 | ||
| 1 | 931件 | ||
| 合計 | 2656件 |
(月〜金)昭和の音楽史を代表する作曲家・古関裕而と、歌手としても活躍したその妻・古関金子をモデルに、昭和という激動の時代の中で人々の心に寄り添う数々の曲を生み出した作曲家とその妻の波乱万丈の生涯の物語。
彼女が成仏できない理由でミャンマー(戦時中のビルマ)の文字を知っていたから、
本当にミャンマーの人に申し訳ないと朝から思った。
よその国で戦争する人たちに正義なんてない。
エイミーごめんなさい。
ドラマに出てきたインパールって、よくわからなかった
ので、検索してみたら、これはイギリス軍(イギリスの
植民地のインドの方が徴兵されて?多数参加)と日本が
戦ってるんですね。
でも、ドラマにはイギリスもインドも、全く出てこない
不思議。
現場の悲惨さの接写ばかりで、世界史的には、
どうだったの?っていう視点が大きく欠けている。
エールは大好きでずっと見てきたんだけれど、
こういう話が続くなら、見る気がなくなってしまう。
窪田正孝さんは不正を正そうとした会社の若手を自殺に見せかけて殺す半グレ役のほうが似合うと思う。悪役でなくてもノワール物が似合う。
眉根にやたら力入れてるし、顔立ちが闇が似合うというか。
いずれ東野圭吾さん原作小説書いてくれないかなぁ。
浩二、なんで結婚しないんだろうと思ってたら、原節子みたいな女性待ってたのか(笑)
もし日本が戦争をしていなかったら、どうなっていたかという疑問を投げ掛けられている方がいました。
私としては、諸外国の要求を受け入れ、大陸での一部の権益ほ手放してでも、何とか石油などの資源も供給してもらいながら堪え忍ぶ、という選択になると思います。
そのうち世界の状況も変わるかもしれないので、国力がじり貧になっても、外交努力をしながら何とか堪え忍ぶ。国民が我慢できるかどうかがカギですね。ロシアとの戦争の後も国民は十分な戦利品が獲得できなかったと、不満いっぱいでした、今でも少しでも税金が増えたり、食料や物品が高くなったり手に入らなかったり、生活が悪くなると、国のせいにしますから。
今週も中々辛い展開が続きそうですが、今の私達にとってもこの時代に起きていた事はとても大事な事なのでちゃんと見ていきたいです。これから裕一の苦悩が少しずつ深くなっていくんだろうなと想像します。頑張れ、裕一。
私は、原節子さんのお父さん役をやっていた笠智衆さんがタイプです。
窪田正孝くんはNのためにの成瀬くんが最高だったけど、この裕一もかなり好き。裕一はほかの俳優じゃできなかったと思う。
裕一は前線にいき戦況悪化の現実を知る。
ドラマではいまいち緊張感というか緊迫感が薄い、朝ドラだからか。
誰も気づかない視点として、裕一はにほんと言っていた。軍人はニッポンか。
庶民はにほん、軍人はニッポンと言うことで使い分けているのか、戦争という観点からして正しい。
ニッポンという言い方はある意味明治史観。
古代史から説明すると長くなり理解してもらえないと思われるので割愛致します。
ミャンマー軍は今も、軍艦行進曲と愛馬進軍歌のメロディを使っているようだ。古関さんのは受けなかったのかな?
昔のフィルムとか着色できないのかな?その方が現実感が出ていい。
古関さんは「神風特別攻撃隊の歌」まで作ったというか、作らされたんでしょうけど、そこまでしたのか日本軍と思うような異常な事態だったこと。兵隊は単に戦争の道具にしか思ってなかったんじゃないかと、戦争を語り継ぐ元日本兵の方がテレビで語っていたのを思い出します。インパール作戦は戦後70年の番組で知りました。酷すぎますよ、人間の考えることじゃないっていうやり方が通っていたんです。
浩二はなぜ出征しない。
オープニングに脚本家の名前がないと思ったら最後に出た。作・演出 吉田照幸。先週からこの人が書いているがやはりその筆は厳しく、役者に要求するものも視聴者に突き付けるものもけっこうきつい。いよいよ演出も自分でやるらしい。今週辺りがこのドラマの肝だと思うので、しっかり見ていきたい。
裕一がビルマに到着。どうやら裕一の日記とモノローグで描いていくらしい。朝ドラの後半とは思えない立派なセットで驚いた。今日は役者もまた上手い人を揃えていて、かなり気持ちを入れ込んで見ることができた。
到着の挨拶時はまだ朝ドラを見ている気分だったが、しだいに画面が暗くなっていき、ヒタヒタと迫りくる緊迫感、不穏な音楽。現地の子供達の手紙にすき焼きを囲んでの談笑から、最後は前線の地獄の様子。日本とビルマ、慰問先と前線の落差を強く印象付ける。「つづく」の文字が出た時は朝ドラを見ている感覚ではなくなっていた。どうなるんだ一体。裕一と同じ気持ちになる。裕一の語りの声、歩き方、ここからどんどん変わっていくと思う。
音と華は福島へ。まさが床に伏せっていると三郎を思い出す。浩二はあの時の三郎のおかげですっかり打ち解けている。
音と浩二のシーン。兄ちゃんが心配かと問う浩二に、すぐには返事ができない音。音が心配しているのは裕一の命はもちろんだが、それだけでもない様子。しかし裕一の変化を見ていない浩二にはそれがわかるはずもない。傍から見れば浩二のこの感覚が普通だろう。
この二人の会話は微笑ましかった。何より、あのぶすくれ顔の浩二があんなに柔らかい笑顔を見せるなんて。感無量。しかし浩二の理想が原節子だったとは。このままでは結婚は遠そうだ。
星は先週の分。私は今作がここまで戦争を深く描くとは思っていなかった。朝ドラでここまで戦争を描く作品を私は初めて見る。素晴らしいものを見せてもらっていると感動している。始めは批判もあった裕一が作曲家なのに楽器を全く使わずに作曲すること、ドラマの雰囲気が昭和っぽくないこと、明るく楽しいドラマだが時にとんでもなくシリアスになること、どれもこの戦争編に見事に繋がっている。この時期は裕一のモデルである古関裕而の名誉にも関わる大事な時期。彼と彼の作った楽曲にしっかり敬意が払われていると感じる。そしてドラマの伝えたいことが、丁寧に描いただけあって、視聴者にもちゃんと伝わっていると思う。土曜日曜の間に素晴らしいレビューがたくさんあり、その中で10-10 19:01:16さんに いいね をつけさせていただいた。
戦後も(現在もか?)女性差別はあったが、戦前の比ではない。
しかし国防婦人会では、例えば遊郭の女たちもいったん割烹着と襷を身につければ「平等」にあつかわれたようだ。市川房枝や平塚らいてうは、手放しではないものの、ある種の女性解放をもたらしたとしてこの団体活動に一定の評価を与えている。
女性の自立がこんなところから始まったとは…。
浩二は原節子派だったんだね。自分は、高峰秀子さんか、李香蘭さんがいいな。
原節子!浩二も裕一も、、、やっぱり兄弟ね。笑
何度見ても凄いですね。
朝ドラクオリティーじゃないです。
短編映画のようです。
浩二も丸くなってきたな。この時世でも仕事は順調なのか?
国防婦人会班長のような人は、平時には面倒見のいい、「仲人ばあさん」みたいな人なんだよね。戦争が終わったならそんな人が認めてくれるはず。希望は控えめにしよう。
これまでたくさん感動をもらってきたエールですが、今日のストーリーは、あんまり……
いきなりミャンマーに到着、状況説明もないまま、裕一は軟禁されているみたいになっていて。
東南アジアの国の人々がどういう立ち位置なのか不明。そこに軍隊を置いているヨーロッパの国々の立ち位置がどうなのかも語られないし。その時の日本側の考え方もよくわからないし。
裕一は狭い部屋に子供みたいにポツンと置かれて、何十日もぼーっと過ごしているだけ。メモ書きも断片的、奥歯にものがはさまったみたいな内容。
カビとかサソリとか、ミャンマーの描かれ方が残念すぎて、これをもしミャンマーの人が見たらどうなのかな。
情報が遮断されすぎているし、裕一なりの考えや感じ方も何もないし……ドラマとしても、今日はひきこまれるものがあんまり……
「好きなタイプは?」「原節子みたいな・・」それを聞いて返答に困る音。今日唯一クスッと笑える場面だった。戦後世の中に希望と明るさを与えた映画「青い山脈」で原さん演ずる島崎先生の気品あふれる笑顔が思い浮かぶ。
先日、ある専門家グループのOB会に出席した時、好きな女性のタイプで盛り上がった。
「スマホを使わないで公衆電話をかけている人がいい」
「電車でスマホを使わないで文庫本を読んでいる人がいい」
「レジや電卓でなく、五つ玉のソロバンで会計してくれる人がいい」
「電気釜でなく、かまどでご飯を炊いている人がいい」
「車に乗らず、自転車で青い山脈を歌っている人がいい」
という、原節子世代の方たちってまだいるんですね。
戦争を深く描いてるとは全く思わない。裕一の戦中の苦悩は描かれるのだろうが、戦争の状況は説明不足でしょう、どの朝ドラも。
いよいよ戦争編が終盤を迎えました。裕一は激戦地で想像を絶する戦争の悲惨さを知る。音と娘華は裕一の母親の見舞いを兼ねて福島へ疎開した。音は裕一が育った部屋で戦地にいる夫を思う。関内家では戦時下の中、質素な暮らしをしていたが婿の五郎は軍に収める馬具作りに後ろめたさを感じていた。それぞれの環境で健気に懸命に生きる人たちがこの先悲しい戦争に巻き込まれていくと思うと胸締め付けられる。コロナ禍で今まで当たり前だと思っていた暮らしが失った時代に朝ドラで戦争を描く意義があると思います。当たり前な暮らしや尊い命を奪う不幸な戦争のあやまちが繰り返さないようにドラマを見て顧みる必要があると思います。
ずっと視聴率がふるわないところを見ると、コロナ渦に戦争の重い空気を入れるのは、コアな朝ドラファンなら別だが、一般的には受けてないのだろうと思っている。今週も気が重い。しかし直太朗ファンなので見届ける。
森山直太朗さんの反戦歌「夏の終わり」
夏の終わりにはあなたに会いたくなるの♫
奥さまに歌わせないで。
視聴率は大河も落ちたまま戻らないね。麒麟とエールはもうこのままかなあと思う。最後はどちらも上がると思うけど。コロナで当初の予定が大きく狂ったからしょうがないね。
今再放送中の「純情きらり」も戦時中だけど、朝ドラらしい戦時中だなあと思う。リアルさより感動重視。それもまた一つの良さ。今日の桜子ちゃんはきれいだわあ。
「エール」は全然違うと思う。人々の生活、心理の中にある戦争。一般市民には戦況は知らされず、まして世界情勢など知るよしもなく、また知ることが重要とも思っていなかった時代の人々。色々と考えさせられる。
『映像記録史 太平洋戦争』とか『映像の世紀』とか普通に観てた者だけど、皆様の感想読んでると、軍歌ばかりなようで……観てない。
ドラマを誘致した福島・豊橋の方々はこういったシーンも含めて期待してたんですよね。
全て無謀で無駄な死・・・まさに犬死にです。
来ましたよ。
洗脳来てますよ。
騙されちゃいけませんよ。
インパール作戦。
戦う以前に食糧不足で餓死者続出の無謀な作戦と
糞みそに貶されてる作戦です。
実はこの作戦、
インド人に感謝されているという事をご存知でしょうか。
日本の国自体が危なかったあの時期に、
インド独立のために戦われたものなのです。
イギリスの歴史家エリック・ホブズボームは、
このように言ってます。
「インドの独立は、
ガンジーやネルーが率いた国民会議派が展開した
非暴力の独立運動によるというよりも、
日本軍とチャンドラ・ボースが率いるインド国民軍(INA)が
協同して、ビルマ(現ミャンマー)を経由し、
インドへ進攻したインパール作戦に依ってもたらされた」
この戦争の意義のようなもの、前に指摘されているような世界がこの時どうだったかとかは、敢えて一切触れていないのだと思います。あくまでも大衆にとってあの戦争はどういったものだったか、翻弄された一般の人々を描いているのでしょう。
何を描きたいのかよくわからないお話。
外の世界をもう少し描くための慰問だと思ったから、肩透かしでした。たこ壺みたいな、井の中の蛙みたいな世界観。
裕一には何も知らされないとしても、ドラマを見ている人には、もう少し、多角的にその時代を見せてほしかった。
想像力がないとついていかない展開。
想像力が大事です。
作家の人、戦争を伝えるのが作家の務めって勇気あるなぁ。
画家の人も戦争を描こうと途中までは行ったけど、作曲家は子供たちと歌うか曲を作るかなのかな。
確かに歌手の方が喜ばれるのかもしれない。
ビルマと聞いたら竪琴を思い出す年代です。
しっかり読んだことはないが中井貴一さんが坊主になってた映画は印象にある。
ビルマがビルマに見えない。
裕一のナレーションばかりでつまらない。
従軍画家とか作家とかどのくらいいたんでしょうか。
向井潤吉さんという日本のかやぶき屋根の民家の絵を
多く残した方の絵がとてもリアルで好きなのですが、
従軍画家だった経験から対象を素早く描くことが
できるようになったと聞きました。
戦後消えていったかやぶき屋根の田舎家の絵を残したことは
従軍経験と無縁ではないと思います。
日本の原風景の絵ですので興味ある方は見てみてください。
全ての職業の人が、戦争勝利のために動員された。
従軍陶芸家とかいたんでしょうか。
井の中の蛙といえば、、、思い出されるあのドラマ。
それはさておき、実際、裕一(を含む民間人)はずっと戦争の実態を知らされてなかったのだから、井の中の蛙という表現は当たっているのかも。今、裕一は日本を出て、井戸のふちにいるところだと思う。
今でも日本人は、井の中の蛙ですよね。対戦相手のことがほとんどドラマに出てこないなんて。
映画『ビルマの竪琴』で中井貴一さんは肩に乗せたインコに耳たぶを噛まれて痛かったと公開当時の本人談。
「自分は帰るわけにはいかない…」というセリフがあったと記憶している。
浩二の婚活は贅沢を言わなければ何とかなります。福島の有名呉服店を潰し、要介護度2の母がいるのは若干マイナス。とりあえず公務員で家持ちのプラスもある。
マサを見送って、終戦となれば、若い男の少ない時代、何とかなると思います。有名な兄は、マイナスなのか、悲しい。
浩二の婚活は贅沢を言わなければ何とかなります。福島の有名呉服店を潰し、要介護度2の母がいるのは若干マイナス。とりあえず公務員で家持ちのプラスもある。
マサを見送って、終戦となれば、若い男の少ない時代、何とかなると思います。有名な兄は、マイナスなのか、悲しい。
浩二がんばれ、あとは人柄。
インパール作戦の現場指揮官は牟田口廉也という陸軍中将で、これがまたとんでもない指揮官で、武器も食料も全く不足しているにもかかわらず精神論だけで部隊を前進させ続けた。戦闘でもさることながら餓死や病死した兵も多かったんでないかなあ。まさに地獄の戦場だね。
古関裕而さんと一緒にビルマへ慰問にいっていた作家の火野葦平さんは、彼が残した手帳の中で ” 前線にダイナマイトを100キロ送ると50キロしかないと報告がくる。兵隊が食うのである。 ” とかいていたんですよね。つまり、ダイナマイトの原料であるニトログリセリンは、少し口に含むと甘い味がするので、それで飢えを凌いでいたということです。果たして、このドラマでは、そのようなことをきちんと描けるのでしょうか!? まぁ、ちょっと無理だと思うんですけどね!!
局所的な話しをすると、日本がインドやアジアの解放、独立のための助けになったということはあっただろうが、日本が戦ったのはあくまで自国のためであった。インパールもそうだろう。
アジア諸地域の独立は、日本が介入しなくても20世紀に入ってからの世界の潮流として、いずれ自らの力で成し遂げられたと思われる。ウィルソン米大統領が当時提唱した「民族自決」は主として欧州の白人に対してであったが、それを契機としてアジアにも独立の機運が高まったからだ。むしろ日本は対華21ヶ条などでそれに逆行するような行動をとった。
ただ、ウィルソンの言う民族自決が果たしてどの民族にとっても得策かと言うと疑問はある。全ての民族が自立しそれぞれ別の国を作るのが果たしてその人々にとって豊かで幸福になる方法なのか。多民族が一つの国で同じ権利の下で、それぞれの特徴を生かし補完し合って行くほうが遥かに得策である場合もあるだろう。
そう言う意味では、日本は手段やプロセスや統合の形態はまちがっていたが、概念としては正しかったのかもしれない。
しかしそうはならなかった、ウィルソンの民族自決は、必要以上に民族間の抗争を世界各地に広げてしまう結果を招いたと思える。
兵隊さん達はダイナマイトを食べていたんですか?
当時の日本は史上最低最悪な状況でしたね。
二度と戦争は起こしてはなりません。
それを、エールは丁寧に伝えて下さい。
先週から凄い、戦争に真摯に向き合ってる観てるこっちは、思いを巡らして泣きそうです、いや泣いてる場合じゃないわ、ミャンマーの兵隊、突きつけられた、
こんなに必死に守ろうとしてくれた兵隊さん
今の日本をどう思うのか
スパイ天国と言われ、隙だらけの国
国を守るとは、
エールは、きついながら深い。
裕一の日記は古関裕而さんが書いたものを参考にしているのかな。
そういったものがあったのかどうかは知りませんが。
『いだてん』では金栗四三さんの日記文が引用されていたのを思い出しました。
日記があるかは知りませんが、たしか自伝は書かれていたと思います。それをもとにしているかもしれないですね。裕一がやがてあの日記を書き続けることができなくなるのではと、ちょっと怖いです。
インパール作戦は、現代を生きる軍事素人の私ですら無謀な計画だったと思う。
ドラマでは雨季に入っていたから、現地は昭和19年6~7月頃かな。
マラリアにも要注意だね。
すき焼きを皆で食べていたのはラングーンだよね。
「ひよっこ」みね子の宗男叔父さんもいたインパール攻略作戦。飛行機を使って大量の物資を運んでいた連合国に対し、無謀にも陸路で移動するという無謀な作戦で、愚将牟田口廉也中将の積極策もあって多くの死者を出すことになった。その中に藤堂先生もいたとは。
スポンサーリンク