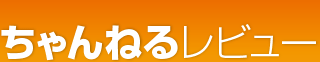3.96
3.96
| 5 | 237件 | ||
| 4 | 76件 | ||
| 3 | 48件 | ||
| 2 | 21件 | ||
| 1 | 55件 | ||
| 合計 | 437件 |
おみごとな論破です。
>初めに非難ありき、の歪曲としてしか理解できない。
始めにありき非難の根拠をぜひお聞かせ願いたいです。
自分自身はこの大河ドラマはかなり手堅い作りの一般的感覚、大雑把な幕末史の知識を持ち合わせている人には十分受け入れられるもの、と感じていますが、このドラマのみならず大河ドラマそのものへの憎悪すら感じるコメントを書かれた方がなぜそこまで憎しみを抱くに至ったか、については興味があります。
二本松少年隊の生き残りである、水野好之氏の回顧録「二本松戊辰少年隊記」によれば、木村銃太郎が被弾負傷し、動けなくなったため、副隊長の二階堂衛守に命じて自分の首をはねさせた。
その後、銃太郎の首を髪を左右に分かち、二人の少年が運んだとのこと。
藩侯の菩提寺、大隣寺の前の広場までいくと、数十人の兵士がしきりに手招きするので、助かったと喜び近づいたところ、一斉に発砲され、二階堂はじめ、数人が射殺されたり、負傷して生け捕りにされるものもいた。
少年たちはばらばらになって、逃げたり戦って死んだりしたが、水野と4人の少年たちは土湯で会津藩士に保護されたとのことでした。
この手記をもってすべて史実とは言わないが、「八重の桜」での少年隊の悲劇の描き方は、お涙頂戴どころか、相当、新政府側に配慮しオブラートに包んだものである。
この回を一方的すぎる歴史観と批判する人がいるが、水野氏の回顧録からすれば、まだまだ甘いくらいであることも、知って頂きたいです。
1.
いや、どうみても「無抵抗の子供の虐殺」を意図した演出ですよ。
薩長兵が少年兵に気づいたのは戦闘終結後でしょ。
少年隊に抗戦能力があったことを描きたいならそれを示す戦闘シーンを差し込むべきだし、
薩長方の勘違いを描くなら薩摩方の陣地も交互に映すべきだった。
2.
つまり、ドラマの演出のため史実を捏造したというわけですね。わかります。
ところで、今回の戦闘を抽象化すると
「何の役にも立たない小学生並みのヒョロガキが
薩長方の温情にもかかわらず狂乱して返り討ちに会いました」
っていうしょうもない話になってるんだけど、どうなの?
会津観光史観には反対の立場だけど、これはちょっとかわいそう。
3.
>武道とは、究極的には殺人兵器の取り扱いの指導である
そうだよ。だからこそ武道の指導者は「武術を軽々しく使うな」と口を酸っぱくして言うだろ。
八重には自分が扱っている道具が殺人兵器であること、
砲術が殺人術であることの葛藤なんて全くないんでしょ。
だから軽々しく殺人術を少年たちに教え込むし、
仇だの恨みだのとかいう斜め上の思い込みに向かう。
少年だろうと鉄砲を向けたらただの敵だよ。
しかもその鉄砲は八重が教えたもの。恨みを抱くなんて筋違い。
>おみごとな論破
勝利宣言乙
>二本松戊辰少年隊記
それが史実だと思うならそれをベースに描けばいいだろうに、
薩長方への配慮(笑)の挙げ句つまらない展開しか書けないようじゃどうしようもないね。
少年隊員の心情も真面目に描かず無慈悲に撃ち殺されて死ぬだけの役割。
紀行で「決戦前夜は修学旅行みたいだった」っての聞いた?
ドラマ中の少年隊員の顔ぶれ、少年隊の戦いぶりを見た後でその様子が想像できる?
こんなところでディベートの練習はやめてほしいな。
他の人が感想を書きづらくなる。
で、この論戦に勝った後に何が残るの?
感動したという人の心は変わらないし、つまらないという人の心も変わらないよね?
つまらないという感想を書くのは自由だけれど、楽しんでいる人をバカにするような書き方をする必要はないんじゃない?
自分はこのドラマ理屈抜きで好きだし、素晴らしいと思うので、言葉遊びに使われるのは凄く嫌ですね。
ここはドラマのレビューサイトです。
感動した、あるいはつまらなかった理屈を書く場所です。
理屈抜きにつぶやきたいだけならTwitterでどうぞ。
>紀行で「決戦前夜は修学旅行みたいだった」っての聞いた?
ドラマ中の少年隊員の顔ぶれ、少年隊の戦いぶりを見た後でその様子が想像できる?
私は想像できますけど。それに紀行での話は想像もへったくれもなく事実でしょ。ドラマは創作物。歴史ドラマと言えど歴史を題材にしただけの虚構の世界。修学旅行のような風景をドラマに取り入れればあなたは良いドラマになったと思う訳ですか?
だってそもそもあなたの主張だとこのドラマはじじいや歴史オタが好むような歴史をなぞったドキュメンタリーなんじゃなかったの?
二本松少年隊が史実と同じように描かれたらドキュメンタリーだ、と批判する立場をとってたんでしょう?
なぜ同じ人間が正反対の主張をするのでしょう?言ってることが支離滅裂。歴史やらドラマやらいう前に論理的思考を養えるお勉強をした方がよろしいです。
そもそもなんで疑問形で書くの?誰もできませんね、なんて同意しないよ。自分が想像できないならなぜかという理由を書いて自分の主張をするのが感想というもの。
ほぼすべてにおいてまるでドラマの感想になっていない。
ドラマが好きでも嫌いでもいいけれど他の人が読むものなのだから人間が読んで理解できる理屈は通してもらわないと困る。
ディベートにもなっていない。もしディベートというなら勝利があまりに明らか過ぎて読んでいても全く面白くない。
いちいち人の言葉尻をとらえて面白いですか?上の上の人が言ってる事、そういう意味ではないですよね。
どうせああいえば、こういうだから、何を言っても無駄なんだね。
21:59:07さん
あなたが理屈をこねるのは勝手だが、下にも書いてあるように、「ファン同士の対立を煽るような書き込みは行わないでください」という節度は守るべきではないですか?(ファンじゃないとかそういう屁理屈はやめてくださいね)
結果としてあなたの挑発的な書き込みで、ここはケンカのようになってきてますよ。
このドラマが好きな人を不快にさせないような批判の仕方だってあるんじゃないですかね。
先に「二本松戊辰少年隊記」を書き込んで、心無い人に笑われたものですが、私は「八重の桜」でこのエピソードを極力抑えたことは正解だったと思います。
元隊員の回顧録で史実に近いとはいえ、戦場で子供たちが隊長の首を持って逃げ回ったり、新政府軍に手招きをうけて騙し打ちで打たれるような描写は、ドラマとしてはふさわしくないと思います。 そうでなくても凄惨な回でしたから、薩摩兵の手記の方のエピソードを使ったことで末端の兵たちの心の葛藤をよく表現できたし、少年達の混乱した心理とよくまじり合ったと思います。(そう思わない人もいるみたいですが、私はそう思いました)
ただ、今回の放送がとりわけ新政府軍を意図的に悪く描いたものではなく、こういうエピソードだってあるんですよという意図で「二本松戊辰少年隊記」に触れました。
ちなみに、新政府軍にもいろんな人がいたでしょうから、刺されながらも「少年だから殺すな」という人もいれば、騙し打ちで殺してしまう人もいたのでしょう。資料が矛盾してるとか言いそうな方がいらっしゃるので。
いちいち反論とか気にしながら書くのはしんどいですね・・。早く以前の平和な掲示板に戻ってほしいです。
>早く以前の平和な掲示板に戻ってほしいです。
全く同感です。
いや同じものを見ても感じ方が違う人がいるのは当たり前だからいろいろなコメントがあっていいし、だから面白いのですが、ドラマの感想欄を賛否の対決欄だと勘違いして他の人の人間性の部分まで含めて徹底攻撃するような人間が出てくるとこうなるんですね。
それこそここは戦場じゃないんだよね。
銃の使い方を全く分かってない人がやみくもに鉄砲ぶっ放してるみたいな印象。
世の中から戦争がなくならないのはなぜか、を見せられてる思いです。
一般民衆にとっては平和が一番なんですがねぇ。
4月に最重要拠点「白河城」が攻激され、奥州列藩は会津を中心に守りを固め激戦となる。二本松藩はすぐ援軍を送り込んだが退路を絶たれ帰藩できなくなり、この戦で最も剛健なる主力兵の大半も失い結局落城。そして7月には、小藩の守山藩が堕ち、近隣の三春藩も危ないので、二本松藩は援軍として”なけなしの精鋭部隊”を送り込んだ。
しかし三春藩は既に官軍に寝返っていて、彼らをを二本松まで先導した上、あろう事か援軍の二本松藩に砲撃。この時の犠牲者は、最低でも60人という。
二本松藩の霞ヶ城は家老以下、18名の重臣達は、全て悲壮な最期を遂げ、あの時点で残っている藩士は、15歳以下の子供と老人と16~17歳が数名のみ。しかも約20数名程の隊士の内13~15歳が圧倒的に多かった。そして砲術隊長木村銃太郎(22歳)が撃たれ、子供達だけが取り残された。悪いことに彼らは八重が教えた銃で応戦した為、薩摩側は応戦が終わって近寄ってみるまで、まさか”子供達だけの隊”とは知らず、激しく動揺した。
そこで薩摩側の小隊長は「殺すな!」と命じ、無事保護された子供も居たし、虫の息の子供に頼まれ、泣きながら解釈した兵も居た。尚、この藩は貧しく、畳を盾にしたのも事実のようです。
要するに小椋桂氏の歌詞のように”時の流れの激しさに”対応する間もなくあっという間に敵が攻めてきたので、子供達までが巻き込まれたようです。その後の城下の女性達が被った悲劇は想像を絶するものでしょう。
”介錯”のまちがいでした。すいません。現代の常識から見て「??」と思ったら、この時代からまだ150年足らずで、生存者もいた為に詳細な証言(薩摩藩側からも)も有るので、現地に行くなり、ご自分で調べてみたらいかがでしょうか。
八重と尚之助の会話から使われていた銃が関ヶ原の頃と同じような火縄銃が多いと知って
びっくりした。
この時代から見ても300年近く前のものと同じということ。単純計算で今から考えると18世紀初頭の道具を使うようなこと。江戸時代には大きな戦もなかったからもう何代も戦というものから全く離れていた民がそんなものを手に戦に巻き込まれたということだ。
子供が宝のように大事にされるこの国で子供までもやむにやまれず参戦しなければならなかった同じ国の者どうしのこの戦とは一体何だったのか、と考えさせられた。
こういう時代を生き、こういう経験を実際にした八重という女性が新しい世でどういう考え方をしてどういう生き方をするのか、作者がどう描くのか楽しみ。
結局戦争の悲劇とか言ってみたって
容保が腹を切らないために藩士領民が死んでるという話。
いくらかわいい子供たちが死んだところで
同情の前に容保とその家臣に対する怒りが込み上げてくるだけ。
いいんじゃないですか。世界の中心で一人でそう感じてれば・・
結末が分かっている後世の人間から見れば、容保の判断ミスと簡単に片づけられるのだが、当時は藩主の首を差し出すなど藩士が絶対許さなかったし(長州藩ですらやらなかった)、既に容保を守るために何人もの藩士が亡くなってるわけだから、容保としてはおいそれと勝手に死ねない立場であったと思う。
結果が重大なだけに、容保に腹が立つという見方も理解できますが、彼の生真面目さや誠実さが、これ程にもあだとなってしまうような世の理不尽さが、私的には恨めしいと思いました。
古代から幕末、近代と、人間は知恵と技術に関しては大きく進歩したものの、感情のコントロールや道徳心においては、まったく進歩してないんだなと感じるこの頃です。
何人もの藩士が死んでるから
・もう無駄な戦争はやめよう→慶喜
・意地でも戦争を続けよう→容保
史実通り描いたら共感できないキャラになるのは明らかなんだから
もっと脚色してあげれば良いものを
正義は人の数だけある!
一年かけて大河をやる意味もそこにある。
どの時代、どのような人々が、何を信じ、どのように生きたか。
現代とは考え方も生き方も違っていてあたりまえ。
それをどのように描くか。
興味深く観て、感じていきたい。
感じ方も人それぞれ。観るか観ないかも人それぞれ。
それにしては会津の世界観が安っぽいな
殿を守るのは義務だから当然って感じでもないし
容保にもっと人徳者の雰囲気を出せばよかったのに
八重も八重で恨みと憎しみでしか行動できないのは大河の主人公としていかがなものか
逆恨みされる薩長の兵隊も可哀想だ 彼らにも家族や友人がいるのに
慶喜は無駄な戦争をやめようとしたというよりは、
結局、手に余ったものをすべて会津にぶん投げた。
そういう風にしか見えなかったな。あくまで主観だが。
陣保修理をはじめ、命がけで藩士一同殿を守ろうという気持ちは、私には痛いほど伝わりました。不器用ながらも誠実な殿の人徳あってのものでしょう。
八重は復讐心もあったであろうが、これ以上故郷を蹂躙させたくないという使命感の方がより強く表れていたと思う。こういう状況でも負傷者をやさしく介護するという行為は憎しみのみに憑かれた人間には到底できないと思うので。
そう感じる人もいるということで、感じない人がいてもいいと思います。
ただし、22:17:43さんの、感じ方も人それぞれと争いを抑えようとしたコメントの後に、それにしては・・と蒸し返して決めつけたような発言で再度挑発する手法には、もううんざりです。
↑気持ちはわかりますが、あまり過敏になりすぎないように!!
ここは戊辰戦争の続きをする場ではないのですから^^;
山本覚馬の「管見」のシーンで、
「敗れても、滅びても残るものはある」この言葉に感動。
同時に、「鬼神」とまで言われた覚馬が力士のような声
になって弱弱しくなってしまったのがちょっと寂しい。
綾瀬はるかのなまった口調がすごくわざとっぽくてちょっと……
というか綾瀬はるか主演なのに演技下手すぎ
ホタルノヒカリの干物女の時は上手かったのに…本気出してないのかなぁ…
綾瀬さん十分うまいです。
というかうまくなった。現代劇でしか見たことなかったけれど演技力も女優としての貫録もこのドラマで着実について来ていると感じます。
会津ことばをあそこまで彼女が自然に話してくれるとは正直予想外。聞いていても濁点の多いあの言葉を自然に聞こえるようにするためには役者さん達かなり努力していると感じます。
西田敏行さんのが一番自然なのだろうと思いますが、自然すぎて時々ホントに分からない時あります(笑)。
薩摩や長州、土佐もこのドラマではお国ことばにこだわっている。
大河でもここまでこだわってる点は珍しいし素晴らしいと思います。新選組の土方なども生粋の江戸っ子勝海舟ともまた違った多摩のことばに近いものをちゃんとしゃべってる。
しかし当時は絶体こんなにお互い言ってること、すんなりとは通じなかったんだと思います。
るろうに剣心でさえOVAはR指定なのに。
江戸時代の武家公用語は能楽の言葉。
会津の陣屋で会津弁を話すのは好きにしたらいいが、
江戸城内な宮中のような公共の場所でお国訛りしているのはかなり恥ずかしい。
>江戸時代の武家公用語は能楽の言葉。
このようなデタラメをまことしやかに断言するのはやめて頂きたい。
「武家公用語」などと言うものは存在しない。少なくとも武家社会に「公用語」があった、などということが何か記録に残っているなどと聞いたことがない。
能楽のことばとは何のことを言ってるのか?謡曲の詞章のことか?
能楽は江戸時代には式樂と呼ばれるようになるまで武家の間には浸透し、お抱えの能楽師を持つ藩もあり、謡曲は武士の教養となった。当時は感覚としては藩が今で言う「国」のような感覚でありそれぞれ方言が強く、お互いに何を言ってるのかほとんど理解できない場合も多かった。それぞれの口語そのままでは話が通じないために文語を用いて意思疎通をはかったらしいことは事実であるが、その場合ほとんど武家では書き言葉として一般的であった漢文が多かった。謡曲もほぼ漢文調の文語体であるが、謡曲をすべて覚えていたとしてもそれをそのままの形で共通語のように使って会話するなどどう考えても不可能。謡曲には節がついているので共通のアクセント、イントネーションを伝えることができるから、言いたいことを漢文にしたうえでその節にのせて伝えれば伝わる場合があった・・・残されている記述としての資料はせいぜいそこまで。
本当に大事なことは筆談で取り交わしたはず。
西郷と勝の江戸城明け渡しについても正式な記録として残っている。
江戸城内や宮中で謡曲を持って会話をしていたなど聞いたことがない。江戸時代は参勤交代もあり江戸住まいをする各藩士も多くなったり、江戸との行き来が活発になったため、公の場で、時代が進むにつれて上方ことばよりも江戸ことばが多く話されるようになったとは言えるだろうが、音源が残っている訳でもなく、実際にそれぞれがどのような言葉で話していたかなど知る由もない。ましてや宮中で謡曲のことばが話されていたなどあり得ない。
一体何を根拠にそのようなことを言うのかはっきりと書いていただきたい。
単にドラマに対してケチをつけたい、中傷したい、という目的だけのために事実でもないことをあたかも事実であるかのように出鱈目を述べる行為はやめた方がいい。
ドラマなどというものではなく、そういう行為こそ「かなり恥ずかしい」かぎりだ。
このように軽率極まりない行為からしてこれまでの主張にもまるで説得力がないとしか感じられない。
他の人が何か書けばすぐにいやがらせのようなことをいちいち書く行為を繰り返す目的は何なのか?
多くの人が不快感を感じるような行為を繰り返すのは著しいマナー違反ではありませんか?
延々とこのような行為を続け、ドラマが終わるまで週1で★1をつけたいだけなのかもしれませんが、単なる「憎しみ」は「感想」「レビュー」と言えますか?
他の人のコメントにいちいち茶々を入れて場を荒らすようなコメントは
削除して頂きたいです。
この国に「標準語」の概念が誕生するのは明治時代後期です。
「日本語」という範疇に入る言語しかないこの国で「公用語」という概念は過去にも現在にもないのでは?ことばの使い方として個人ベースで私用語、公用語というならわかりますが、それなら口語のみにそれを限定するのはおかしいです。
大河ドラマの表現をこれがすべて日本の歴史であると鵜呑みにすることも現代人の視点のみからそれを批判するのも実にナンセンスだと思います。それが好きか嫌いかは感性の問題であり別問題。個人的感性に後付けで理屈をつけてドラマや他の人を否定できると考えるのは大間違いです。
ある視点から見た歴史を題材として人間を描くのが大河ドラマであることは普通の人なら十分承知でしょうし作者も視聴者のほとんどもその共通理解の上に立ってこれまでもドラマが作られ楽しんで来たのだと思います。
八重の桜はドラマとしていろいろな意味で変なクセや歪みが感じられない非常に見やすい大河ドラマと私はこれまでのところ感じています。
いやはや歴史オタの巣窟になってますな。歴史オタとパソコンオタは知識を自慢するところがいかん。知っててもノーベル賞も取れん無駄な知識なのに。
武家に公用語がなかったら仕事にならねえじゃん。
藩士の相当数は国許におらず江戸詰なのにお国言葉に拘ってられる訳がない。
庶民の口語や言文一致を言ってる訳でもないのに何熱くなってるんだか。
半年経ってもまだ幕末か?やっぱりという感じ。幕末なら視聴率が取れるからね。
明治時代はどう扱うか新鮮な感じがして興味があったんだが?
そもそも新島八重なんて大河で扱うほどの人物だったのか?
あっという間の45分でした。
猪苗代城での斎藤一と土方がすごくよかった。
「会津の女ではなく会津そのものに惚れた」
「俺は俺の戦いをする」
このやりとりはベタで何度も目にしているが、
登場した頃は、覚馬や山川にガンを飛ばしていた斎藤が
ここまで義を貫こうとする姿勢にしびれる。
来週が待ち遠しいような、でも来週を思うと胸が苦しくなる。
茶々いれてる人達はもう、どうでもいいです。
>庶民の口語や言文一致を言ってる訳でもないのに何熱くなってるんだか。
一人で熱くなっていちいち難くせつけまくってるのは誰でしょうかね?誰が見ても一目瞭然。
武士に公用語が無かったら、ってそれは漢文だったに決まってるじゃん。ちょっと歴史知ってる人ならそんなの常識。どこの誰が文章を方言で書くなんて考えるのさ?
書き言葉にしても話し言葉にしても、この時代の日本にどこに「公用語」という認識があったのかちゃんと書きなよ。
そもそも人のコメントを元に自分が問題にしてたのは口語のことでしょ?
教養がまるでない人間が他の人をオタとか言うのってとんでもなく恥ずかしいよね。
二本松藩は「人が好すぎる」、或いは愚直と思える程の”義に厚い”、自らを顧みず「他藩を救おう」と援軍を出すその心意気に大変感動しました。しかもそれが裏目に出て、肝心の城下の守りが手薄になり、残った少年達が戦わざるを得なかった事。そして彼らが銃で勇猛果敢に戦い、後世「戊辰戦争中第一の激戦」と言わしめた事。こんな凄い史実が「賊軍、逆賊」の汚名を着せられた上、白虎隊の陰に隠れて埋もれたままで、福島県民でさえほとんど行かないのは、不思議で理不尽で、気の毒で残念でなりません。白虎隊は飯盛山から、煙の上がる「鶴ヶ城」を眺めた時、「落城・・?!もはやこれまで・・」と早合点して帰還して戦力になる事無く、自刃してしまいました。こちらはそれより更に歳下の、わずか二十五名のまだ心細かろう子供達が、堂々と激しい銃撃戦をして、隊長が、友が銃弾に倒れる中、弾が尽きるまで戦い抜いて官軍をたじたじにさせたのですから、白虎隊よりも高く評価されてもいいのでは?と思います。
あれから一世紀半過ぎて、十代前半で散った少年達のお墓の前で、私達がその勇気を称え、哀悼の涙を流すだけで、天国の彼らに気持ちは必ず届くと思うので、東京駅から二時間程の二本松市に、皆さん、是非行ってあげてください。
福島はこれまでごく一部しか訪れたことがないのですが、このドラマを見ていろいろな所をゆっくり訪ねてみたい気持ちになっています。大河ドラマの舞台になっている地を訪れるのは結構好きです。オンタイムで行くと大河ドラマ館とか各種お土産グッズなどもいろいろあるし、知らないこともいろいろわかりドラマが倍楽しめる感じがします。
八重がいよいよ出陣ですね。自分が戦いたいという気持ちがあっても薙刀ではなく銃や大砲、となると女性の身で戦場に赴くのがいかに難しい世の中だったのか、という描写が当時をちゃんと描いていて、八重のもどかしさ、悔しさがひしひしと伝わって来ました。
三郎の軍服を着て弟と一体になって、という演出がこれまでの経緯と重なっていて良い脚本、演出だと思います。
綾瀬さんの激情を内に秘めた演技も素晴らしいと思います。もちろん会津藩の前途多難で悲しい先も見えてはいますが次回が楽しみです。
もちろん戦を肯定したくありませんが、役者さん達の引き締まった表情には皆さん凛々しく迫力がありますね。照姫さまもこれまでで一番美しかったです。
白虎隊のことは結構ドラマや小説などで知っていましたが
二本松少年隊のことは名前を聞いたことがあるくらいであまり
よく知りませんでした。
そういう意味でもこのドラマを見てよかったと思います。
旧幕府軍側から見たドラマでなければここまで詳しく奥羽での
戦の様子など取り上げられませんからね。
そういう意味でも貴重な作品かもしれません。
新選組の土方と斉藤が会津まで一緒だったことは知っていましたが、
斎藤が会津に残り土方は仙台→五稜郭へと転戦して行く二人の
別れの場面なんていうのも初めてドラマで見ました。
> 武家に公用語がなかったら仕事にならねえじゃん。
これ書いた人って他の人が書いた文を読み取る能力がまったくないんだね。
まあだから言ってることが支離滅裂、滅茶苦茶なわけだ。
荒らしそのもの。
ほんとどうでもいいわ。
読まないことにします。
しかし場所だけ取ってうっとうしい。
八重の母も女性が戦場に赴くなんて言語道断、のように八重を諌めていましたが、三郎の軍服に身を包んだ八重の決意の固さにはそれ以上言葉が出なかったのでしょうね。
息子たちを失い、今また大事な娘を失うかもしれない。
戦場に我が子を送り出さなければならない母はいくらそういう時代でいつでも覚悟はしていた、とは言えどんな気持ちだったか、今では想像を絶するものがあります。
死を覚悟した頼母に、老いてもなお息子に武士の心得をぼそっとつぶやく小さな姿が何だか
とても印象的でした。
だから8人も十人も子供を産んでるのでは?
俺のばあちゃんは9人産んで戦争とかで4人しか残らなくても平然としてたよ。
昔は人間の命の価値なんかひどいものだったと思いますよ。なにしろ病気や飢饉でどんどん死ぬ時代ですから。現代は美化しすぎ。
たしかに今は昔みたいにどこの家にも子供がごちゃごちゃいっぱいいるとかないから多少は感覚ちがうかもしれない。
昔の親は今より大らかだっただろうし。
でも何人いても子供はどの子も大切に思ってたのは今も昔もそうは変わらないんじゃないかと思うけど。
いっぱいいるから少し欠けてもいい、なんて思って子を育てる親、我が子が戦争に行って死んで平気な親なんていないでしょ?
平然と見えても昔の人は気丈だったから今の人みたいに表だってめそめそしなかった、ということはあると思う。
頼母の小さいお母さんは、戦に向かう男が家のことなんて心配するな、というようなこと言ってたけれど、あれは息子にあれこれ案ずることなく武士としてまっすぐに生きろ、という武家の教育の建前であり、武家の母独特の愛情の表し方に見えた。
武家に生まれた者はいつでも主君やお家のために命を捨てる覚悟はできてる。でも山本家の父だって筋を通しつつ、竈の前で号泣していた。昔も今も人の心の奥にあるものはそうは変わらない。でなければドラマは成り立たないと思う。
前回久しぶりに見ましたが引き込まれました
白虎隊はあまりしらなくて放送をみたあとぐぐってみましたが
こんな悲しい歴史もあったんですね
ただ相変わらず主人公の影は薄く感じました
おかげでドラマとしては散漫な印象になっているかもしれません
女性が主人公の大河ドラマ(歴史ドラマ)はどうも苦手で45分ほとんどヒロインが出ていたりするとかなりつまらなくなってしまうことが多かったので今回の八重くらいが私はちょうどよく感じています。私には八重の心情も良く伝わって来るし、女性が表舞台に立てないことに疑問を感じながら、地道に銃の訓練や制作をし、芯が強いけれどとげとげしかったりきつく見えない八重は好感が持てます。感じ方って人によって違うのですね。
それよりもここのところ毎回、頼母中心に会津の家老たちの間で方針をめぐっての話し合いの場面が時間的には短いながら大河らしくてすごく好きです。
どの視点からでもいいけど政治劇をおろそかにしない大河は個人的に見てて面白いです。
これまで半年描いてきたストーリーの重みがまったく感じられない。
八重が立ち上がる背景は結局「弟の仇」。ちなみに根拠はないが兄は生きているらしい。
こんな展開なら最初から会津戦争でも変わらなかったのでは?
でもこの脚本家はオリジナルエピソード描くのが下手だから
史実をぶつ切りに追ってきた今の展開のほうがまだマシだったかな?
また来ましたか・・。
どう思われようが人それぞれなので、あなたはそう思うのですね。
一つだけ、「根拠はないが兄は生きてるらしい」って、兄の覚馬は先週も先々週も登場してますよね。
そんなことも抜けていて、自信たっぷりに辛口評価されても苦笑しか出ないです。
全く同感。ドラマに対して賛成でも反対でもちゃんと見ないで単なる個人的好みで書かれたようなコメントは、ああそうですか、そう感じるだけですね、で終わり。
でも他の人のコメに茶々入れてるわけでもないですからまあ・・
ドラマ終わるまで✩1をつけ続けるのが目的に見えますし。
批判があってももちろんいいと思います。でも独りよがりで具体的場面や描写との関連がなにもないコメントは読んでもおもしろくないし説得力皆無です。八重主人公でこの時代でどんな描き方ならよいとおっしゃるのでしょうか?それをこのドラマと結びつけて具体的に書いて下さるともっと読みたくなる感想なのでしょうが、申し訳ないけど、何かの理由で憎しみを持っているのだろうな、くらいに見えます。
八重が立ち上がった理由が「弟の仇」だけって見えるというのは不思議。
ドラマってその人がその時だけに言った言葉を短絡的にとらえて見るものじゃないのでは?
一話から八重のことはずっと描かれているし八重の性格や個性、考えてることは
前のエピソード通してふつう分かると思うけど。
スポンサーリンク